未経験からエンジニアを目指したいけど、失敗して後悔したりしないかな…。
これまでと全く違う業界に転職するには、大きな不安が伴い勇気が必要ですよね。
本記事では、未経験からエンジニアになった人が後悔しやすいポイントと対策をまとめました。
実際に事務職から組み込みエンジニアに転職した私自身のリアルな体験談もお届けするので、エンジニアを目指すか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
未経験エンジニアが後悔しやすい7つの理由
1-1. 覚えることが多すぎて想定外だった

未経験からエンジニアになってまず驚いたのは、「覚えることの多さ」です。プログラミングの基礎だけでなく、現場では以下のような幅広い知識が求められます。
- 開発環境の構築(エディタ、コンパイラ、デバッガなど)
- チーム開発のルール(ソースコード運用、レビュー対応)
- 開発プロセス(要求分析、設計、コーディング、テストなど)
上記は組み込みエンジニアの場合の一例で、求められるものはエンジニアの種別によっても異なります。
また、会議では技術用語や略語が飛び交い、最初のうちはほとんど会話についていけませんでした…。未経験者にとっては“何を知らないかも分からない”状態で、強い不安や後悔を感じてしまうかもしれません。
さらに現場では、教えてもらえる環境が整っていないこともあります。自分で調べ、仮説を立てて試行錯誤する力が必要とされ、「こんなに自学が必要なの?」とギャップを感じる人も多いのです。
しかし裏を返せば、それだけ成長のチャンスがあるということ。事前に基礎を身につけておくことで、現場での吸収力も格段に変わります。まずは小さな目標を決め、確実にステップを踏むことが後悔しない第一歩です。
1-2. 転職直後は収入ダウンで生活が苦しくなることも

未経験でエンジニアへ転職すると、多くの人が直面する可能性があるのが「収入ダウン」の問題です。特に前職で安定した収入があった場合、年収が50万〜100万円以上下がるケースも少なくありません。
なぜ収入が下がるかというと、企業側は未経験者を「これから育てる人材」として扱うため、スキルや実務経験に応じて低めの給与設定にする傾向があります。特にSES(客先常駐)や中小IT企業では、その傾向が強く出ることもあります。
手取りが減ったのに、家賃や生活費は変わらない…
子どもの保育料やローンが払えなくなりそう
など、転職後に生活が苦しくなり、後悔する人もいます。将来性を見込んで転職したはずが、現実とのギャップに不安を感じてしまうのです。
ただし、エンジニアはスキル次第で収入が伸びやすい職種でもあります。実務経験を1〜2年積めば、年収アップやより良い職場への転職も現実的です。そのため、最初の1年は「投資期間」と捉えて、生活設計をしっかり立てておくことが大切です。

私の場合も転職してから1~2年後に評価が上がって収入も増えました!
1-3. コミュニケーション能力が重要すぎる

「エンジニアは黙々とコードを書くだけの仕事」と思っていませんか?
自分もそう思っていた一人だったのですが、現場ではコミュニケーション能力が非常に重要です。未経験で転職してきた人の中には、ここでギャップを感じて後悔するケースもあります。
- 分からないことを先輩や同僚に質問する
- 進捗ミーティングで進捗報告や困りごとを相談する
- 顧客の要求を聞き、不明点は会話で聞き出したり整理したりする
- メールやチャット等の文章で簡潔に問合せする
たとえば、設計書やテストの仕様を見て不明点があった場合。
周りの人が忙しそうで聞きづらかったり、チャット等で聞くにも質問をまとめるのが難しくて時間がかかったり等、コミュニケーション不足で仕事が思うように進まないことも多いです。
また、レビューのフィードバックをどう受け止めるかも大切です。最初のうちは技術力の不足からレビューでの指摘も多く、
「こんな初歩的なことを指摘されるなんて…」
「また指摘された点を修正しなきゃ…」
と落ち込むこともしょっちゅうでした。しかし、そういった指摘を1つ1つ見直して修正していくことで確実に自分のスキルアップにつながっていきます。指摘されても落ち込みすぎず、成長のチャンスとして前向きに受け入れる姿勢が必要になります。
さらに、チームでの開発では「報連相(報告・連絡・相談)」ができないと、プロジェクト全体に影響を与えることもあります。逆に言えば、技術力が未熟でも、報連相をしっかり行うことで信頼を得られることもあるのです。
エンジニアにとって、「分からないことを伝える力」もスキルのひとつ。最初はうまくいかなくても、少しずつ慣れていくことでコミュニケーション力は確実に伸びていきます。
1-4. 求人広告とのギャップ「思っていた仕事じゃない」

未経験歓迎!
自社開発あり
やりがいのある仕事
———転職サイトでよく目にする求人広告の言葉。しかし、いざ入社してみると「実際は違った…」と感じ、後悔する未経験エンジニアも少なくありません。
とくに多いのが、「開発をやると思っていたのに、テストや資料作成が中心だった」というケースです。未経験者がいきなりコードを書くポジションに就けることは稀で、まずは補助的な業務やテスト工程からスタートするのが一般的です。

私も最初の数ヶ月はひたすらテスト工程でした
また、「自社開発」と書かれていても、実態は受託開発がメインだったり、SES(客先常駐)で他社のプロジェクトに配属されることもあります。このようなギャップは、転職後のモチベーションを大きく下げてしまいます。
求人広告は、企業側の都合の良い表現がされていることも多いため、言葉をそのまま鵜呑みにしないことが大切です。たとえば「未経験歓迎」と書かれていても、実際には実務レベルのスキルが暗に求められている場合もあります。
ギャップを防ぐには、面接時に仕事内容を具体的に確認することや、口コミサイトや転職エージェントを活用して“企業の実態”を調べるのが効果的です。入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、事前リサーチは欠かせません。
1-5. 研修・教育の制度が不十分で教えてもらえない
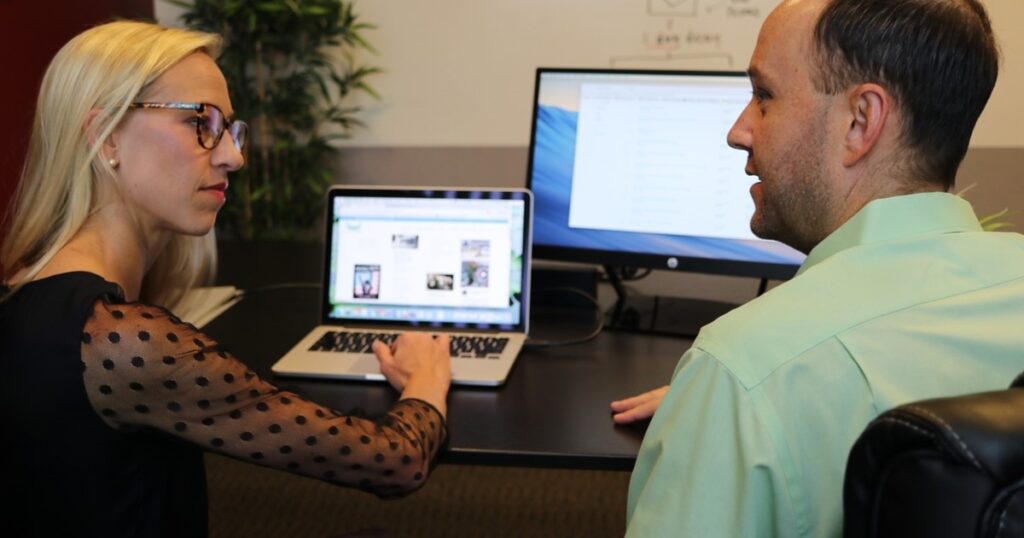
「未経験OK」と書かれていたので安心して入社したのに、実際は放置に近い状態だった
これは未経験エンジニアの後悔あるあるの一つです。期待していた研修がなく、教育体制も整っていない現場は想像以上に多く存在します。
人材不足の企業では、そもそも研修の時間や人員を割けないことも多く「実務を通して覚えてね」というスタイルが一般的です。マニュアルも整備されていない場合、何をどこから覚えればよいか分からず、強い孤独感や不安に襲われることがあります。
また、「分からないことがあっても聞きにくい雰囲気」「質問しても答えが返ってこない」といった、相談しづらい環境も後悔の原因になります。とくにエンジニア文化には“自力で調べて解決するのが当たり前”という風潮があるため、未経験者にはハードルが高く感じられます。
こうした状況を避けるには、入社前に「教育制度は具体的にどんな内容か」を確認することが重要です。たとえば「何週間の研修があるのか」「メンター制度はあるか」「OJTはどのように進むか」など、具体的に聞くことでリアルな体制が見えてきます。
自分に合った育成環境を選ぶことが、転職後の後悔を減らす大きなポイントになります。
1-6. キャリアパスが見えず将来が不安になる
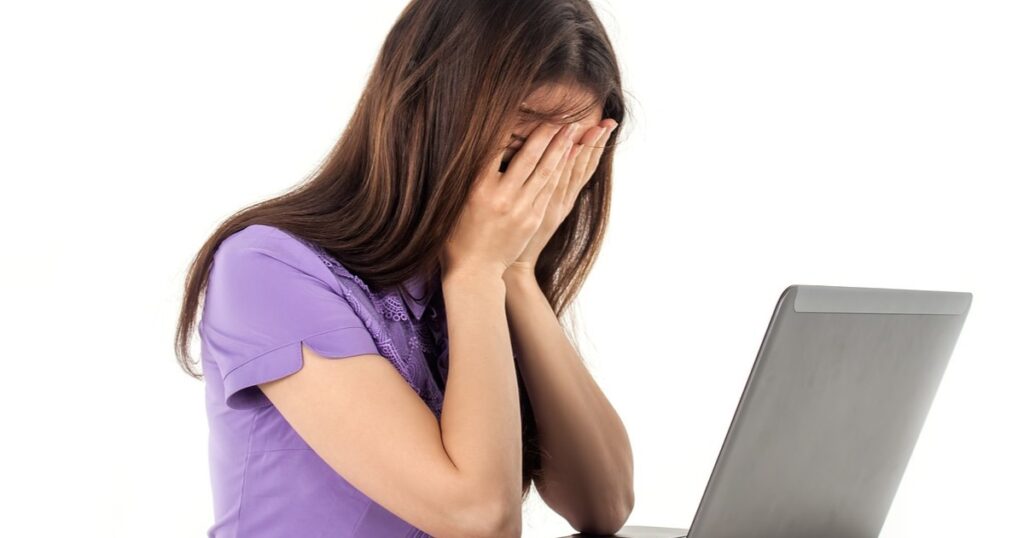
未経験からエンジニアになったはいいけれど、
この先、自分はどうなっていくのか分からない…
と不安になる人も多いです。実際にエンジニアになった私自身も、良く悩んでいる問題です。
日々の業務をこなすのが精一杯で、気づけば何を目指せばいいのか分からなくなり、将来のビジョンが描けず後悔することがあります。
特に、テスト業務や運用保守などの補助的な仕事が長く続くと、「いつになったら開発ができるの?」「キャリアアップできるの?」と疑問を感じるようになります。企業によっては明確なキャリア制度がなく、成長の方向性を示してもらえないこともあります。
こうした後悔を防ぐには、自分でキャリアの方向性を決め、逆算して行動することが大切です。
具体例をあげると以下の通りで、自分の進みたい道に合わせて意識的にスキルの幅を広げることが求められます。
- 開発チームの管理職になって現場を指揮したい! → 技術力だけでなくマネジメントの勉強をする
- 製品開発を支援する業務につきたい! → 品質関連や開発プロセス関連の勉強をする
会社に任せきりにせず、自分自身でキャリアのハンドルを握ることが、後悔しない道をつくる鍵になります。
1-7. 「自分には向いていないかも」と感じる瞬間がある

未経験からエンジニアになって最もつらい瞬間は、「自分には向いていないのでは」と感じてしまうときです。

私も何度も何度も何度も感じて、正直辞めたいと思ったり、時には涙する日もありました…。
既存のソフトや設計書を読んでもなかなか理解できず、同僚のスピードについていけなかったり、何度も同じミスを繰り返してしまったり…。そんなとき、「やっぱり自分には無理だったのかも」と自己否定してしまうことがあります。
特に、IT業界特有の“常に勉強が必要”というプレッシャーに押しつぶされそうになる人は多いです。周囲にバリバリ勉強している人や優秀な人が多いと、「自分はこんなことで大丈夫かな?」と不安に襲われ、気持ちが沈みやすくなります。
また、論理的思考や抽象的な概念が苦手だと、コードの構造やエラーの原因が見つけにくく、「そもそも自分はエンジニアに向いていないのでは」と思い込んでしまいがちです。
ですが、こうした悩みは誰もが一度は通る道。向き・不向きの前に、“慣れていないだけ”というケースがほとんどです。
大切なのは、「今できないこと=一生できない」ではないということ。焦らず、自分のペースで一歩ずつ進むことが、結果的に大きな成長につながります。
また、自分と人を比べすぎないことも大切です。
エンジニアは優秀な人が多く、他人と自分を比べると苦しくなりがちです。しかし、他人ではなく過去の自分と比べてみることで、成長を感じられて自己肯定感アップにもつながります。
後悔しないためにできる対策
事前に覚悟すべきことを整理する
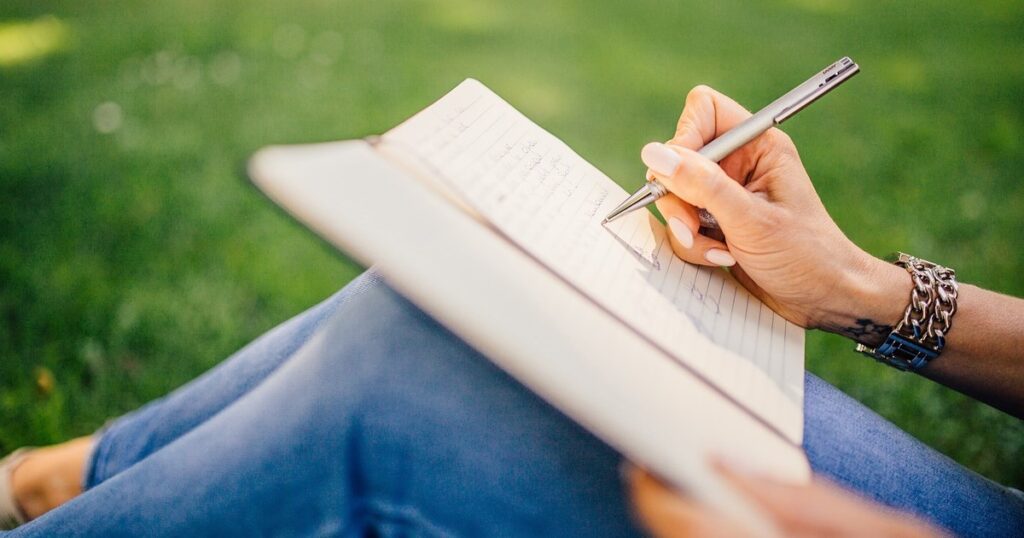
未経験からエンジニアを目指すなら、スタートラインに立つ前に覚悟すべきことを整理して、「何に苦労するか」を理解しておくことがとても大切です。華やかなキャリアチェンジの裏には、地道で地味な努力が必要な現実があるからです。
- エンジニアになるために勉強時間の確保が必要
- エンジニアになった後も半年~1年は勉強と実務の両立でかなり忙しい
- 収入が下がるリスクがある
- 自信を失ったり、自己肯定感が下がる場面もある
それぞれ説明していきます。
①エンジニアになるために勉強時間の確保が必要
働きながらエンジニアを目指す場合、勤務以外の時間で勉強時間を確保する必要があります。

私も事務職から組み込みエンジニアを目指していた時期は、通勤中、帰宅後、休日の時間を使ってひたすら勉強していました。
未経験でもエンジニアは目指せますが、「勉強せずに楽に稼げる」という世界ではありません。
ゲームしたい、遊びたい、友達と飲みに行きたい…そんな気持ちをぐっとこらえて、意識的に勉強時間を捻出する覚悟が必要です。(もちろん時には息抜きも大切ですが)
②エンジニアになった後も半年~1年は勉強と実務の両立でかなり忙しい
エンジニアになるのがゴールではなく、むしろスタートです。最初の半年〜1年は「勉強と実務の両立」でかなり忙しくなることを覚悟しておきましょう。
日中は慣れない業務に追われ、夜は自己学習や復習に時間を使う毎日が続きます。特に子育て中や家族がいる方は、時間とエネルギーの使い方に悩むこともあるでしょう。
③収入が下がるリスクがある
1章でも取り上げましたが、転職によって一時的に収入が下がるリスクもあります。
いったん年収を落としてでもスキルを身につけたいのか、それとも今の生活水準を保ちながら転職したいのか、自分の優先順位を明確にする必要があります。
④自信を失ったり、自己肯定感が下がる場面もある
学習や業務の中で「分からないことが分からない状態」に陥り、自信を失ったり自己肯定感が下がる場面もあるでしょう。
そんなときに備えて、誰かに相談できる環境や、心の支えになる仲間をつくっておくのも有効です。

覚悟とは、ポジティブな諦めでもあります。
「最初はうまくいかないのが当たり前」「しんどい時期もある」と割り切っておくことで、壁にぶつかったときに冷静に乗り越える力が育ちます。
“理想”だけではなく、“現実”も見据えてから転職活動をスタートさせることで、後悔を減らし、成功への道をより確かなものにできます。
入社前に企業情報をしっかり調べる

未経験からエンジニア転職を目指す人が後悔しないために、企業選びの段階での情報収集は最重要ポイントです。ここを疎かにすると、「思っていた仕事内容と違った」「研修制度がない」「残業が多すぎる」など、入社後のギャップで挫折するリスクが高まります。
- 業務内容を具体的に確認する
- 教育体制やフォローの有無
- 口コミサイトで企業の実態を知る
それぞれ説明していきます。
①業務内容を具体的に確認する
求人票には「システム開発に携わる」とあっても、実際にはテスト作業や運用保守ばかり…という場合も少なくありません。
面接時には「最初の1年はどんな仕事を任されるか」「どの工程から携われるか」など、具体的に質問してみましょう。
②教育体制やフォローの有無
入社後の教育体制やフォローの有無も重要なチェックポイントです。「メンターはつくのか」「OJTの流れはどうなっているか」「研修期間はどれくらいあるのか」など、育成環境を具体的に聞くことで、自分が成長できる職場かどうかが見えてきます。
メンターとかOJTって何…?
という方に向けて、簡単に説明するとこんな感じです。
| 項目 | メンター | OJT |
|---|---|---|
| 目的 | 精神面のサポート・キャリア相談 | 業務スキルの習得 |
| 指導内容 | 悩み相談、モチベーション維持 | 実務的な作業や手順 |
| 指導する人 | 入社、年齢の近い先輩など | 上司や先輩社員 |
| 方法 | 定期面談や雑談ベースの相談 | 開発現場で直接教える |
| 効果 | 長期的な成長・定着率の向上 | 即戦力化 |

自分が転職した頃はメンターなんて聞いたことなかった気がします…。
精神面のサポートしてくれる人がいるのは大きいので、要チェック!
③口コミサイトで企業の実態を知る
企業の実態を知るには、口コミサイト(例:OpenWork、転職会議など)の活用も有効です。現場の雰囲気や残業の実態、離職率など、求人には書かれていない“リアル”を知る手がかりになります。
面接では緊張して聞きにくいかもしれませんが、逆に言えば、こうした質問にきちんと答えてくれる企業こそ、誠実で信頼できる職場である可能性が高いです。納得して転職を決めるために、「質問する力」も転職活動の重要なスキルです。
スキル習得のロードマップを作っておく
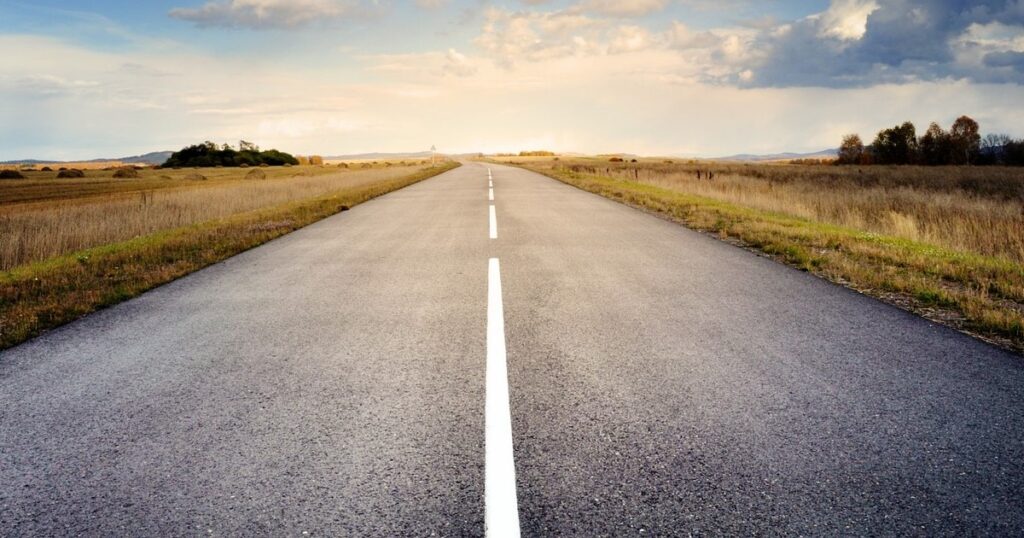
未経験からエンジニアを目指す上で、「何を、どの順番で学ぶのか」を決めておくことは極めて重要です。なんとなく勉強を始めてしまうと、途中で迷子になりやすく、時間もモチベーションも浪費してしまいます。
- 目指すエンジニアの職種を明確にする
- 基礎 → 応用 → 実践のステップで学習計画を立てる
- 期限を決めて具体的な数値目標を決める
- アプリを活用して学習の進捗を見える化する
①業務内容を具体的に確認する
ロードマップを作る上で一番重要なのは、目指す職種を明確にすることです。
私が会社内で転職した時、他に選択肢が無かったため組み込みエンジニア一択でした。
実際勉強に取りかかってみると、プログラミングだけではなくハードウェアやマイコン、電子回路などの知識も必要なことが判明。とにかく勉強することが多く、苦手な分野も多かったのでとても苦労しました…。

転職前に戻れるなら、もっと色々なエンジニアを調べて自分に合いそうなものを選びたいです!
例えば、「Webアプリを作りたい」ならフロントエンドやバックエンドの技術、「インフラに興味がある」ならネットワークやサーバー知識が求められます。
このように、どのエンジニアを目指すかで学ぶべき技術は全く変わってくるので、まずはそこを明確にして学習内容がブレないようにしましょう。
②基礎 → 応用 → 実践のステップで学習計画を立てる
目標が決まったら、基礎 → 応用 → 実践のステップで学習計画を立てましょう。
入門の段階で「よし、AI搭載した走れるペットロボットを作るぞ!」というような高すぎる目標を立てると、心が折れて挫折してしまいます。
まずはしっかり基礎を身につけ、少しずつステップアップしていくことが大切です。
③期限を決めて具体的な数値目標を決める
学習期間の目安や、習得したい技術ごとの「期限」も設定すると、行動にメリハリが生まれます。
たとえば、
- 3ヶ月でポートフォリオを完成させる
- 週2回はコードを書く
- 1日1時間は勉強のために時間を確保する
といった具体的な数値目標を立てるのがおすすめです。
④アプリを活用して学習の進捗を見える化する
学習の進捗を見える化するために、学習ログやタスク管理ツール等のアプリを活用するのも有効です。
また、ただ進捗を管理するだけでなく、迷ったときに立ち返る“地図”として機能したり、あとで振り返った時に自分の成長を実感しやすくなるというメリットもあります。
独学だけでなく、必要ならスクールや支援も検討

未経験からエンジニアを目指す際、多くの人が最初に選ぶのが「独学」です。
確かに独学には自由度があり、費用も抑えられるというメリットがあります。しかし、独学だけで突き進もうとすると
何をどこまでやればいいのか分からない…
つまずいたときに誰にも相談できない…
という壁にぶつかることも少なくありません。
そういった不安や孤独感を感じたときには、スクールや支援サービスの活用を視野に入れるのもアリです。最近では未経験者向けに特化したプログラミングスクールや、転職サポート付きの学習プログラムも数多く登場しています。
- 効率的に学べるカリキュラム
- 現役エンジニアからの添削やフィードバック
- 定期的に進捗確認をしてもらえる
- 転職サポート(ポートフォリオ作成支援、企業とのマッチング)
スクールは数万~数十万単位の費用が必要なケースが多く、気軽に通えるできるものではありません。
しかし、必要な知識を短期間で効率よく身につけて、後悔の少ない転職を実現するためには、“時間と手間の節約”という意味での投資と考えることもできます。
最終的には自分の性格やライフスタイルに合わせて、「独学+スクール」「スクールだけ」「独学+コミュニティ参加」など柔軟に選ぶことが大切です。
一人で悩まず、必要に応じてプロの力を借りる。それも、後悔しないキャリアづくりの一歩です。
モチベーションを維持する仕組みを作る

エンジニアへの道は、長くて地道な挑戦の連続です。
未経験からのスタートでは特に、途中で気持ちが折れてしまうことが最大の敵とも言えます。そんなときに必要なのは、気合いよりも“モチベーションを維持できる仕組み”をあらかじめ整えておくことです。
モチベーションを維持できる仕組みの一例をあげると、こんな感じです。
- 小さな目標を設定する
- 学習記録を見える化する
- 一緒に頑張る仲間や応援してくれる人を見つける
- 質問できる場所を探す
- 定期的に「なぜエンジニアになりたいのか」を振り返る
ここからは私の体験談になります。
私の場合は入社した会社の中で事務職から組み込みエンジニアを目指すことになりました。
会社の制度を利用したため、もちろん上司も把握しており私の挑戦を応援してくれました。
また、社内にエンジニアの方が何人もいるので、分からないことがあれば質問できる環境にありました。
- 応援(+進捗管理)してくれる人がいる
- 不明点を質問できる人がいる
当時はありがたみが分かっていませんでしたが、この2点は非常に重要なポイントでした。
まず上司が応援してくれていたので、転職の試験日程もすべて把握されて進捗も確認されます。
なのでダラダラしている訳にもいかず「試験日までにこれだけ勉強しなきゃ!」ととにかく気が引き締まって受かるために必死になれました。
また、独学(特にプログラミング)していてつまづくと、調べてもよく分からないし中々進まずやる気を失ってしまいます。
しかし、身近に質問できる人がいると1人で1日考えて分からないことが5分で解決する場合もあるので、学習効率もあがりどんどん理解が進むので勉強も楽しくなります。

頼れる人がいるのって本当に大事です!
「継続は力なり」と言いますが、頭で理解していても実践するのは難しいです。
しかし、仕組み次第で解決できることもあります。意志に頼らず、行動を自然と続けられる環境を整えることが、後悔しないキャリアの礎になります。
まとめ:後悔しない未経験エンジニア転職のために
「未経験からエンジニアになって後悔した」という声には、多くの“想定外”が含まれています。覚えることの多さや、理想と現実のギャップ、職場環境のミスマッチなどは、事前の準備やリサーチ不足によって起こることがほとんどです。
しかし、逆にいえば、「後悔しない転職」は、あらかじめ対策を講じることで実現できます。
まず大切なのは、「なぜ自分はエンジニアになりたいのか」を明確にすることです。その上で、自分のライフスタイルや価値観に合った学習方法・働き方・企業を選ぶ意識が必要です。
そして、いきなり完璧を目指すのではなく、小さく始めて継続することが大切です。モチベーションを維持できる環境を整え、相談できる人や支援サービスをうまく活用することで、独学の限界を補いながら前に進めます。
今回紹介した「後悔しやすい理由」と「対策法」を意識することで、あなた自身も不安を希望に変えられるはずです。
エンジニアという職種は、努力した分だけ結果につながりやすく、キャリアの自由度も高い魅力的な仕事です。準備と心構え次第で、未経験からでも十分に道は開けます。
迷いがある今だからこそ、一歩引いて「自分が何に納得できる転職をしたいのか」をじっくり考えてみてください。その問いへの答えこそが、後悔しないキャリア選択への第一歩です。

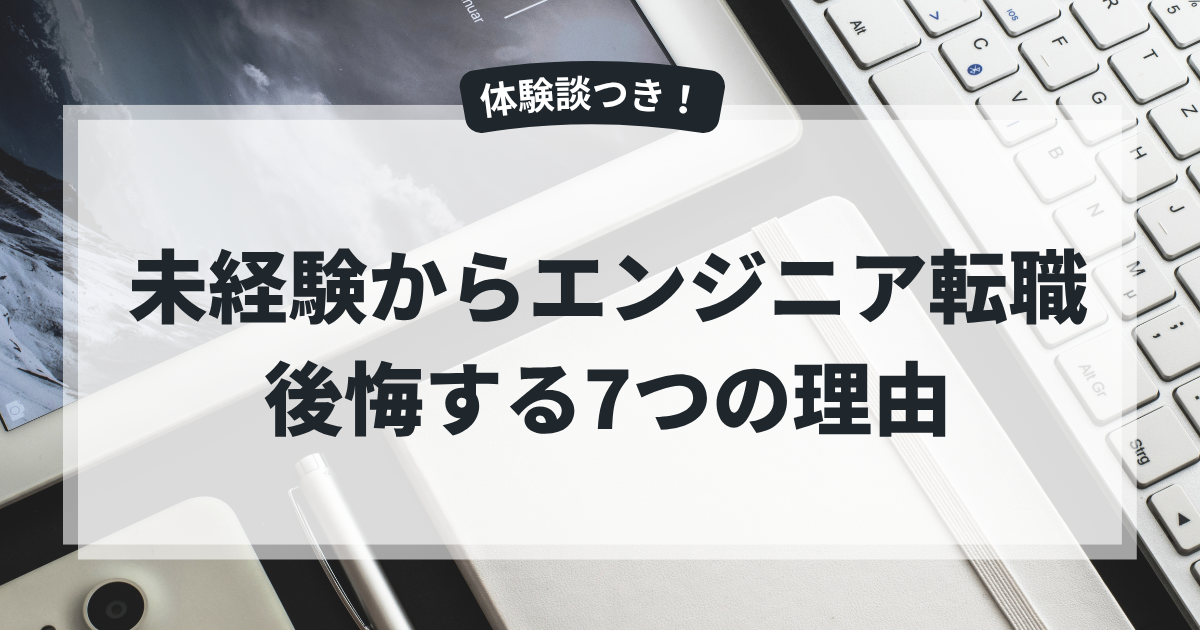
コメント